中国・人民日報国際評論「消えぬ日本軍国主義の亡霊に警戒を」
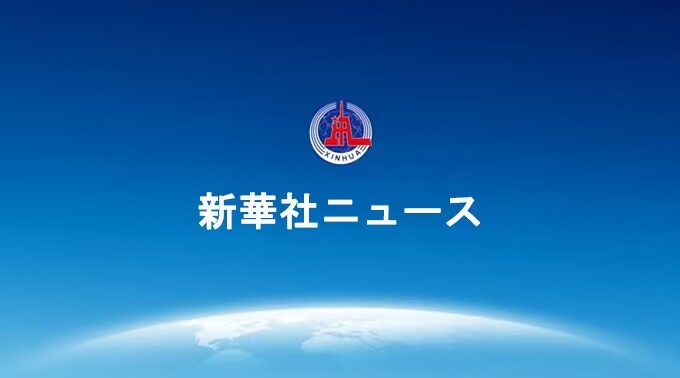
【新華社北京12月26日】中国共産党中央委員会の機関紙「人民日報」は25日、国際評論「消えぬ日本軍国主義の亡霊に警戒を」を寰宇平名義で掲載した。主な内容は次の通り。
日本の長崎市は長崎原爆資料館の展示リニューアル計画で、現在の展示で用いられている「南京大虐殺」という表記を「南京事件」に、「侵略」を「進出」に変更する案を出した。これに対し、一部の長崎市民からは強い反対の声が上がっている。市民団体のメンバー、関口達夫さんは「『侵略』を『進出』という表現に変えれば、日本の侵略で被害を受けた国々の人々は、日本は負の歴史を隠そうとしていると思うだろう」と指摘した。
今年は、中国人民抗日戦争と世界反ファシズム戦争の勝利から80年という節目の年に当たる。第2次世界大戦の敗戦国である日本にとって、本来であれば、軍国主義がもたらした戦争の罪を深く反省すべき年である。しかし、日本の一部の人々や勢力は、侵略の罪を隠蔽(いんぺい)し、美化し、さらには歴史の書き換えを進める動きを強めている。軍国主義の復活さえも図ろうとするこうした行為は、国際社会が共有してきた歴史認識や人類の良知に背くものであり、地域や世界の平和と安定を著しく脅かし、戦後の国際秩序に重大な挑戦を突きつけている。
高市早苗首相は11月初めの国会答弁で、「台湾有事」が日本にとって集団的自衛権を行使し得る「存立危機事態」に当たる可能性があると公然と述べた。1945年の敗戦以来、日本の指導者が公の場で「台湾有事は日本有事」との認識を示し、集団的自衛権の行使と結び付けたのは初めてである。台湾問題をめぐって武力介入の野心を示し、中国に対する軍事的威嚇を公的に宣言するというきわめて踏み込んだ発言だった。こうした一線を越える挑発的な言動は、日本社会において軍国主義の影響がなお払拭されていない現実を浮き彫りにしている。
歴史を振り返れば、日本の軍国主義は対外侵略や拡張に乗り出すたびに、自らを「抑圧され、退路を断たれた存在」と装い、事実をゆがめて国内世論を動員してきた。情勢が整えば、相手に構わず、結果も顧みず、宣戦布告すら行わないまま武力行使に踏み切り、手段を選ばない。現職の日本の指導者が臆面もなく強硬な言辞や行動を示す背景には、こうした軍国主義的思考が色濃く影を落としている。
日本の軍国主義は、かつて対外侵略を主導した中核的な力であると同時に、戦後も右翼勢力の思想的基盤として存続してきた。およそ100年前に用いられた軍国主義的な言説が、今日再び国際社会の前に現れていることは、当時の歴史的清算が本当に徹底されていたのかという問いを改めて突きつけている。
80年前、日本の裕仁天皇は無条件降伏を宣言したが、ラジオから流れた「終戦の詔書」に「降伏」という言葉はなかった。日本は戦勝国の枠組みの下で交戦権を放棄する平和路線を選び、その選択は大多数の日本国民に支持され、国際社会に再び受け入れられる前提ともなった。しかし、戦後の日本で、軍国主義に対する徹底的な清算が完了したとは言いがたい。政府から民間に至るまで、反動的で危険な思潮が繰り返し生まれ、時には計画的な動きとして表面化してきた。「平和国家」を標榜(ひょうぼう)しながら進むこうした「新たな軍国主義」は、アジアのみならず世界にとって現実的な脅威となりつつある。
戦後の「新軍国主義」の醜悪なパフォーマンスは枚挙にいとまがないが、その最も象徴的な舞台が靖国神社であることは疑いない。対外侵略戦争を正当化する精神的装置として機能した靖国神社は本来、日本が侵略の歴史をどこまで正しく認識し、深く反省できているかを映し出す鏡であるはずだ。
靖国神社への参拝は長年、日本の右翼勢力や一部政治家が「新軍国主義」を社会に浸透させるための重要な政治的行動となってきた。高市氏もその例外ではない。2007年8月、安倍晋三内閣の閣僚として参拝して以降、常連の参拝客となり、14年以降だけでも10回以上参拝している。
戦後も軍国主義思想は形を変えて毒を放ち続け、日本の危険な行動を支える政治的風潮と社会的土壌を徐々に形成してきた。政治面では「平和憲法」を形骸化させ、社会の右傾化を加速させている。軍事面では「自主防衛」を名目に軍備拡張を進め、日本をより攻撃性の高い「戦える国」へと作り替えようとしている。文化面では歴史修正主義的な言説が拡散され、教育を通じて若い世代への刷り込みが図られている。外交面では「地域の安全の担い手」を自称しつつ、実際には緊張と対立を繰り返し生み出している。
戦後80年の過程で、日本の右翼政治家は軍国主義に「民主」「法治」「安全」という虚構の衣をまとわせ、自己矛盾に満ちた「新軍国主義」の論理をつくり上げてきた。
こうした動きは中日関係にも深刻な打撃を与えている。台湾問題において、日本は逃れることのできない重大な歴史的な罪と責任を負っている。もともと台湾を「有事」にしたのは日本の侵略と植民地支配だった。戦後、日本は「中日共同声明」や「中日平和友好条約」などの中日間の四つの政治文書を通じ、台湾問題に関して明確な政治的約束を行ってきたはずである。しかし、高市氏の言動はこれらの約束を無視し、両国の相互信頼の基盤を著しく損なった。その結果、中国側の強い抗議や厳正な申し入れ、制裁措置を招いただけでなく、日本国内でも複数の首相経験者を含む有識者から批判と懸念の声が上がっている。
軍国主義の亡霊と日本が決別できるかは、日本という国家と国民がいかにして国際社会と向き合い、信頼を取り戻すかにかかっている。
国際社会は、高市氏に代表される一連の言動が決して偶発的なものでないことを冷静に見極める必要がある。日本は近年、防衛費の13年連続増額、集団的自衛権の制約緩和、武器輸出制限の相次ぐ見直し、「敵基地攻撃能力」のなし崩し的な保有、「非核三原則」の修正論議などを進めてきた。これらは「カイロ宣言」や「ポツダム宣言」によって示された戦後日本の基本的枠組みを徐々に空洞化させ、日本国憲法で自ら掲げた原則にも背く動きである。「新軍国主義」はもはや水面下の潮流ではなく、現実の政策として姿を現しつつあり、世界の平和発展に対する具体的な脅威となっている。
もし高市氏のような言動が是正されなければ、他国にとってもあしき先例となり、一部勢力が既存の国際ルールや秩序に挑戦する口実を与えかねない。それはグローバルガバナンスの根幹を揺るがし、主権平等や内政不干渉といった国際関係の基本原則を損なう危険性をはらんでいる。
日本軍国主義の亡霊がいまだ消え去っていないことは、現実に存在する切迫した危機である。もし日本側が独断的な姿勢を改めず、過ちを重ね続けるのなら、正義を重んじるすべての国と人々には、日本の歴史的罪責を改めて問い直す権利があると同時に、日本軍国主義の復活を断固として阻止する責任がある。これは、戦後の国際秩序を守るために国際社会が共有すべき最低限の一線であるとともに、日本自身が平和的発展を維持できるかどうかを左右する原則的な一線でもある。